
取締役副社長 / コンタクトセンター検定スーパーバイザー
コールセンター業界で8年、管理職としても7年従事し、コールセンター立ち上げやACDシステムの内製化等、運営業務に携わってまいりました。コールセンター運営のノウハウ、マネジメントスキルを活かし貴社のパートナーとしてビジネスの成長に貢献させていただきます。業界特性やニーズに合わせて最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
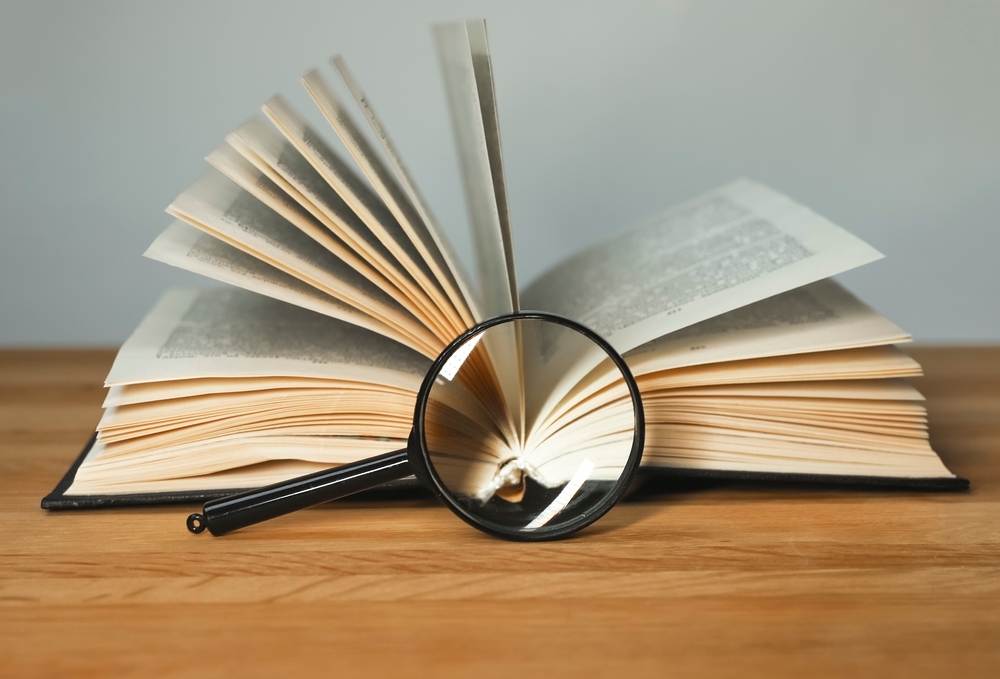
目次
コールセンターは、お客様と企業を結ぶ重要な窓口として、さまざまな業種の企業で設置されています。
「カスタマーサービスを充実させたい」「収益アップや顧客満足度の向上を目指したい」と考えた際には、コールセンターの活用が有効です。
その一方で、専門用語や運営ノウハウに関する知識がないと、コールセンター運営が難しくなることもあります。
今回は、コールセンターでよく使われる専門用語をわかりやすく解説つきでご紹介します。
業務全般または一部を、第三者の業者に委託すること。企業(依頼者)は、事業の拡大・縮小が容易になり、さらには専門性の高いサービス提供が可能になる。
商品・サービスの購入やアポイント獲得を目的に、オペレーターからお客様に対し、電話やメールなどで発信する業務。
▼詳細記事
コールセンターのアウトバウンド業務とは?コツや費用・電話代行サービス紹介まで
対応内容の記録やお客様からの依頼を整理、他部署にエスカレーション依頼など、電話対応終了後の後処理にかけた作業時間の平均値を表す指標。
「After Call Work」の頭文字を取って、「ACW」と略すこともある。
▼詳細記事
コールセンターにおけるACW(平均後処理時間)とは?用語定義や計算方法を解説
商品・サービス購入後やDM(ダイレクトメール)送付後にお客様に電話をかけ、使用感や購入する意思があるかどうか、感想や反応を聞き取ること。
「アベイラブル (available)」は、英語で「利用可能な」「使用可能な」という意味を持つ。コールセンターにおいては、「電話を受けられる状態である」ということ。
お客様からの問い合わせや相談に対して、最初に行う対応のこと。対応次第では、その後の問題解決に大きな影響を与えるため、スムーズな対応を心がける必要がある。
寄せられた問い合わせや要望に対して、オペレーターが一度の対話で解決できた割合を示す指標。なお、最初の入電で問題解決できなかった場合は「二次解決」とみなされる。
「First Contact Resolution」の頭文字をとって、「FCR」と略すこともある。
▼詳細記事
FCRとは?コールセンター用語解説と一次解決率の重要性について
リアルタイムでメッセージをやり取りする、コミュニケーションツールのことを指す。メールとは異なり、実際に会話するような感覚で利用できるため、情報共有や問題解決が素早く行える。
コールセンターに必要な設備や人員を自社内で用意し、運営することを指す。企業自身で構築・運営を行うため、品質管理がしやすく、サービスの品質を維持しやすい。一方、運営コストが高くなるケースも多い。
お客様からかかってきた電話に対応する業務のこと。主に、商品・サービスに関する注文や問い合わせ、クレーム・苦情などの電話を受ける。
▼詳細記事
コールセンターにおけるインバウンドとアウトバウンドの違いとは?
お客様から寄せられた質問や要望、クレーム・苦情などの解決が難しいとき、管理者や他部署の担当者に電話を引き継ぐこと。
▼詳細記事
コールセンターにおけるエスカレーションの意味・対応方法・減らす工夫を解説
応答数に対して、エスカレーションを行った割合のこと。数値が高いほど、管理者や他担当者の負担が大きくなる。負担を軽減するには、オペレーターが対応できる範囲を広げたり、対応スキルを上げたりするための研修や教育が必要。
お客様とコミュニケーションを行うためのチャネルのこと。主に電話やメール、チャット、SMS、ホームページのFAQ、コミュニティサイトなどがある。応対チャネルが豊富であれば、お客様は自分にとって最も便利なチャネルを選択し、問題解決や情報収集を行える。
お客様からの電話やメールなどの問い合わせに対して、オペレーターが実際に応答した数のことを指す。
着信数に対し、オペレーターが応答した割合を示す指標のこと。「電話のつながりやすさ」を表し、コールセンター業務における重要指標の一つとされている。
▼詳細記事
コールセンターにおける応答率とは?用語定義や計算方法を解説
お客様から事前に許可を得たうえで、電話やメールなどのコンタクトをとること。つまり、お客様が自発的にコンタクトを希望した場合にのみ、企業側がコンタクトを行えるため、迷惑電話(案内)と判断されにくくなる。オプトインは、企業とお客様との信頼関係の構築に重要な役割を果たす。
主に電話を通じて、お客様からの注文やクレーム・苦情、質問などの問い合わせに対応する担当者のこと。オペレーターは、コールセンターにおいて最も重要な役割の一つであり、お客様との良好な関係を築ければ、企業の信頼性や評判向上に大きく貢献する。
商品・サービスを利用する際の、お客様視点での体験のこと。具体的には、商品・サービスの選定から購入、購入後のアフターケアなど、お客様が企業と接点を持った過程での感情や満足度が含まれる。
お客様が抱える疑問や問題を解決するためにサポートすることを指す。具体的には、購入前、購入時、購入後にお客様が求めている情報を提供し、顧客満足度を向上させる。
カスタマーサービスを行う窓口・拠点のこと。オペレーターは電話やメール、チャットなどを通じて、お客様のサポートを行う。
期待以上のサービスを提供することで、お客様の心をつかみ、忠誠度を高めることを目指した取り組みのこと。顧客満足度向上だけでなく、顧客ロイヤルティの向上や口コミによる新規顧客の獲得にもつながる。
オペレーターからお客様に電話をかけること。主に、アウトバウンド業務で行われ、キャンペーンの実施やアンケート調査、支払いの督促などを目的とし、架電をする。
一定時間に電話をかけた数を示す指標。時間あたりにかけた架電数が多いほど、架電効率が高いことを意味する。
オペレーターが業務に取り組んでいる時間の割合を示す指標。一般的には、1日あたりの稼働時間から、休憩時間やトイレ休憩などの作業外時間を除いて計算する。
▼詳細記事
稼働率とは?可動率・占有率との違いやコールセンターで重要視される理由
お客様が商品・サービスを利用し、不備や不満が生じた際に、コールセンターに寄せられる苦情や要望、ご意見のこと。
電話対応を終了する際に行う、最終的なアクションや手続きを指す。具体的には、問題が解決されたかどうかを確認したり、商品の購入を促したりするなど、最後までサポートやサービス提供を行う。「クロージングトーク」といった使い方をすることもある。
電話対応に特化した窓口のこと。コールセンターでは、お客様から寄せられる電話に応対するインバウンド業務や、オペレーター自らがお客様に架電をするアウトバウンド業務がある。
お客様からの問い合わせや要望、顧客情報を顧客データベースとして一元管理できるツール。具体的には、お客様から寄せられた問い合わせ内容と、顧客情報を一緒にデータベースに登録。オペレーターは、このデータベースから顧客情報や内容を把握し、適切な対応を行う。
回線が込み合っている、回答に時間を要するなどの理由で、その場で対応できなかった場合、改めてお客様に電話すること。または架電をし、不在だった場合、折り返しの電話がかかってくること。
お客様からの入電内容に対して、適切な問い合わせ先や、対応可能なオペレーターに振り分ける流れのこと。
▼詳細記事
コールフローとは?重要性や設計のメリット・注意点
お客様が電話をかける内容(理由)のこと。「なぜお客様がコールセンターに電話をしてきたのか」を表す言葉で、「コンタクトリーズン」とも呼ばれている。
▼詳細記事
コールリーズンとは?分析すべき理由や重要性について
入電内容に応じて、最適なオペレーターや部署に自動的に転送する仕組みのことを指す。問い合わせ内容やオペレータースキルや状況に応じて、最適なマッチングを行うことが可能。
お客様との電話でのやりとりや、対応内容を記録したもの。コールログには、通話開始時刻や終了時刻、お客様の電話番号や名前、問い合わせ内容、担当オペレーターの名前、解決状況などが含まれる。
商品の使用感や、コールセンターとのやりとりを通じて得られたサービス・サポートに対しての、満足度を表す指標のこと。CS(Customer Satisfaction)とも呼ばれる。
一定期間内に回線を使用していた割合を示す指標。
呼量/コール数は、時間単位、日単位、週単位、月単位などの期間で計測するのが一般的。コールセンターの運営状況を把握するための重要なデータとして、活用されている。
通信回線の混雑や端末不備などによって、電話がつながらずに切られる割合を示す指標。オペレーターが電話に出る前に切断されてしまった場合や、オペレーターが応答できずに呼び出し音が鳴り続ける場合も呼損率に含まれる。
曜日、日、週、月など一定期間において、コールセンターにかかってくる電話の数を予測すること。基本的には過去データを参考に、入電数の波を把握しコール予測をたてる。
▼詳細記事
コール予測(呼量予測)とは?重要性や手法を解説
お客様とコミュニケーションをとることを主な業務とする組織。「コールセンター」と業務内容や目的は同じだが、コンタクトセンターでは、電話以外にメールやチャット、SMSなどでもお客様と接点を持つ。
一度架電をしたが、相手が不在や話し中などで電話がつながらず、時間をおいて再度電話をかけること。
商品・サービスに関する技術的な問題やトラブルに対応するための組織のこと。サポート対象となる商品・サービスに関する専門的な知識が求められるため、トレーニングや教育の充実を図る必要がある。
アフターフォローの充実をアピールしたり、リピーターを獲得したりするために、商品・サービスを購入したお客様に対し、お礼や挨拶に意味をこめて電話をかけること。
スタッフが自分の仕事や職場環境に対して、「どの程度満足しているか」を測定する指標のこと。従業員満足度は、スタッフのモチベーションや生産性、離職率などにも影響を与える。
お客様からかかってきた電話に、オペレーターが対応すること。「インバウンド」とも呼ばれ、主に注文や問い合わせ、苦情・クレームなどの電話を受ける。
お客様からの問い合わせに対して、最初のコールだけで問題・課題を解決した率を示す指標。一次完了率・完結率とも呼ばれている。
▼詳細記事
FCRとは?コールセンター用語解説と一次解決率の重要性について
コールセンター運営を円滑にするために、オペレーターの指導や管理を行う役職のこと。具体的には、オペレーターの応対品質の管理や育成、顧客サポートの改善などを担うポジション。
▼詳細記事
コールセンターのスーパーバイザー(SV)とは?仕事内容ややりがい、必要スキルなど
コールセンター全体の管理と運営を行う責任者。センターマネージャーとも呼ばれる。センター長は、コールセンターの目標達成や業務改善のため、マネージャーやSVの指導、人事管理、予算管理、顧客満足度向上のための施策・実行など、幅広い業務を担う。
一方通行ではなく、お互いの気持ちや意思をやり取りする手法のこと。オペレーター側から一方的に情報発信するよりも、お客様の意思や感情を積極的に収集できるため、顧客ニーズや、企業の改善点を把握するための有効な方法。
▼詳細記事
双方向コミュニケーションとは?コールセンターで重要視される理由
お客様がコールセンターに電話をかけた際に、通話時間や回数に応じて、電話を受けた側が課金されるシステムのこと。「0120」から始まる、NTTのフリーダイヤルが代表的なサービス。
電話対応業務で発生する通話内容や履歴など、通信に関する情報を記録すること。通話ログには、お客様の電話番号や名前、問い合わせ内容、オペレーターの対応内容や結果などが、コールセンターシステムなどに自動的に保存される。
商品・サービスの利用に際して生じるトラブルや問題に対して、専門的な知識や技術を持ったオペレーターが対応する窓口のこと。企業や商品・サービス製品の信頼性や顧客満足度を高めるために欠かせない業務である。
電話を通じて、お客様から寄せられる受注や問い合わせ対応、クレーム対応などの接点を持つ役割。オペレーターやコミュニケーターとも呼ばれる。
主に既存顧客や見込み顧客に対して、電話を用いて商品・サービスの販売促進活動を行うマーケティング手法のこと。
最初に着信した電話をオペレーターが受け取り、それを他のオペレーターや部署に転送することを指す。たとえば、初めに受け取ったオペレーターが対応できない場合や、より専門的な知識を持った部署への連携が必要になった場合に行われる。
かかってきた電話のうち、他オペレーターや他部署に転送した割合のこと。
お客様対応する際の会話の流れを図式化したもの。具体的には、オープニングトークからクロージングトークまでの流れの中で、想定される受け答えや、案内すべき内容をフローチャート形式にしてまとめる。
▼詳細記事
コールセンターのトークスクリプト例文と作成方法解説
トークスクリプトの基本となる会話の流れを表したもの。トークフローをもとにトークスクリプトを作成するのが一般的。
NTTコミュニケーションズが提供する、「0570」から始まる電話番号。ナビダイヤルは、電話をかけてきたお客様が音声案内に従って数字キーを押すことで、オペレーターとの接続や別のオプションを選択できる。
最初に電話を受けたオペレーターが対応に苦慮した場合、SVやマネージャーなどの管理者が代わって応対すること。主に、オペレーターのスキル不足によって、二次対応が必要になるケースがある。
最初に受けたクレームや苦情の対応が不適切であった場合、当初のクレームとは異なる、新たなクレームが発生すること。
すでに商品・サービスの購入や、事前に問い合わせをしているお客様に対し、その後のヒアリングやアフターフォローを目的に電話をかけること。また、リピート購入を目的に新商品の案内を積極的に告知し、収益アップに結びつけるために行うケースもある。
架電をする前に、あらかじめお客様情報や都合などを確認すること。プレコールによって、不在や誤接続などの問題を事前に回避することができる。
お客様から入電があったものの、オペレーターにつながらず、待っている途中で電話が切れたコールを指す。ブロック呼が発生する要因としては、コール量が一定以上になるとACD(着信呼自動分配装置)がブロックするプログラミングが組み込まれていることが挙げられる。
切電後の後処理にかけた作業時間の平均値を表す指標。After Call Workの頭文字をとって、「ACW」とも呼ばれる。主に、対応内容をシステムに記録する作業や、お客様からの依頼をまとめる作業などにかかった時間を測る。
▼詳細記事コールセンターにおけるACW(平均後処理時間)とは?用語定義や計算方法を解説
お客様がコールセンターに電話をかけてから、実際にオペレーターにつながるまでの平均時間を指す。コールセンター運営の状況を把握するための、重要な指標の一つである。
1通話にかかるコストを表す指標。Cost Per Callの頭文字をとって、「CPC」とも呼ばれる。パソコンや電話機器などの設備費、通信費、人件費など、運営にかかわるすべてのコスト要素を含めて計算するのが一般的。
1コンタクトあたりに要したコストを示す指標。Cost Per Contactの頭文字をとって、「CPC」とも呼ばれる。
主にアウトバウンド業務のマーケティング分野に使われ、企業が実施した広告活動などのコンタクト(接触)を行った際に、そのコンタクトに必要とした費用の平均値を表したもの。
1通話あたりのコール開始から後処理終了までに要した平均時間のこと。Average Handling Timeの頭文字をとって「AHT」とも呼ばれる。
AHTの短縮は、業務効率化や生産性向上、コスト削減に大きく影響する。
▼詳細記事
コールセンターにおけるAHT(平均処理時間)とは?用語定義や計算方法を解説
1通話あたりに要した平均通話時間のこと。Average Talk Timeの頭文字をとって、「ATT」とも呼ばれ、コール開始から電話を切るまでどれくらいの時間がかかったかを測る。
「ATTが短い=短い通話時間で効率よく案内できた」ことを意味し、生産性が高い状態といえる。
▼詳細記事
コールセンターにおけるATT(平均通話時間)とは?用語定義や求め方を解説
お客様がコールセンターに電話をかけてきて、オペレーターが応答するまで待った平均時間。Average Wating Timeの頭文字をとって「AWT」とも呼ばれ、AWTが長ければ長いほど、お客様を待たせている時間が多いことを示す。
IT関連にかかわるシステムトラブルや、商品・サービスの使用方法など、各種問い合わせに対応し、解決までサポートする業務・窓口のこと。
▼詳細記事
ヘルプデスクとは?業務内容やコールセンターとの違い
通話録音装置などを用いて、お客様と実際に対話している内容を音声記録すること。通話ログとも呼ばれる。ボイスログは、SVやマネージャーなどの管理者が定期的にオペレーターごとに確認し、教育や指導に活用する。
お客様から着信があったが、オペレーターにつながる前に電話を切られたコール、もしくはシステムが自動的に切電をしたコールのこと。放棄呼は、入電が集中したときに発生する。
入電数に対し、放棄呼数がどれくらいの割合かを示す数値。放棄呼率は、顧客対応能力や業務効率を表すため、サービス品質向上や業務改善において重要な数値といえる。
オペレーターが応答する前に、お客様が待ちきれず電話を切るまでの時間。放棄時間が長いほど、機会損失や顧客離れを引き起こすため、定期的に放棄時間の把握や改善に努める必要がある。
対応方法の確認や他部署に転送するために保留をかけ、お客様を待たせる時間のこと。
オペレーターが対応中に保留をかけたコール数の割合を示す数値。
電話がかかってきているが、コールセンター側の何らかの事情により応答できず、お客様をお待たせしている状態のこと。待ち呼が多い状態は、多くのお客様を待たせており、機会損失や企業への信頼を失いかねない事態といえる。
センター長直下のポジションで、センターの管理・運営を行う役割。主に、稼働状況や応答率などの指標チェック、SVから受けた報告内容をまとめ現状把握を行う。
電話以外に、メールやSMS、チャット、LINEなど、多岐にわたるチャネルをコミュニケーション手段として用い、お客様の問い合わせや要望に対応すること。
複数のコンタクトチャネル(電話、メール、SMS、チャット、LINEなど)を、統合的に管理するコンタクトセンターのことを指す。
電話、メール、SMS、チャット、LINEなどのチャネルからの問い合わせに対応するために、一つのキュー(待ち行列)を設けて、複数のオペレーターがそれぞれの業務を処理する方法を指す。
日付・時間ごとにかかってくるコール本数を、過去のデータや需要予測を参考に予測すること。「呼量予測/コール予測」と同じ意味を持つ。
一定期間内に受けるであろう入電数を予測することを指す。「予測呼」と同じ意味を持ち、業務に適切な人員を配置するために、必要不可欠な要素。
予測コール数は、過去のデータや顧客の傾向、季節性やキャンペーンなどの要因を分析して、予測されるコール数を算出する。
すぐに応答できない場合、お客様が待ち時間を把握できるように、自動音声によるアナウンスで予測される待ち時間を伝えること。
一定期間内に、オペレーターやリーダーなどのスタッフが退職・離職する割合を示す指標。業務内容によって異なるが、コールセンターの離職率は比較的高い傾向にある。その理由としては、業務負担やお客様から寄せられるクレーム・苦情によって、ストレスを抱えることが挙げられる。
業務におけるさまざまなリスクを予防、最小限にするために、戦略やプロセスを実行すること。適切なリスクマネジメントを実施することで、セキュリティリスク、品質リスク、人的リスクを回避し、スムーズなコールセンター運営を維持できる。
既存の顧客リストの中から無効な顧客情報や、入手してから相当の時間が経過した情報を除去する作業のことを指す。リストクリーニングを実施することで、顧客リストを正確な最新情報にできる。
お客様から寄せられた質問や要望に対し、オペレーターが返答までにかかった時間を表す指標のこと。一般的には、問い合わせを受けてから、オペレーターが適切な回答や対応をするまでに要した時間を測定する。
企業がお客様とコミュニケーションを図ったり、プロモーションを実施したりした際、発信数に対する効果の割合を示す指標。
レスポンス率によって、「案内した商品・サービスがどの程度お客様を引きつけるものであったか」「購入まで至ることができたか」を把握し、新規開発や品質向上に役立てられる。
企業や商品・サービスに対して高い満足度を持ち、リピート購入や口コミなどで積極的に推奨する顧客のことを指す。
企業や商品・サービスに対して高い信頼を持っているロイヤルカスタマーが多ければ、リピート購入や口コミによって新規顧客を獲得し、安定した収益に期待できる。
架電をしたが、相手が話し中だった時に流れる「ツー、ツー、ツー、」音のこと。 ビジートーン(BT)とも呼ばれる。
各々のお客様に合わせたマーケティング施策を行い、顧客ロイヤルティを高める手法のこと。たとえば、購入履歴やアクセス履歴を基に、お客様に合わせた商品・サービスの案内やキャンペーン情報のアプローチをする方法が挙げられる。
入電した際、自動的に適切な部署やオペレーターに配分するためのシステム。ACDは、電話回線の自動切換え機能を持ち、複数の電話回線を自動的に整理し、短時間で適切な部署やオペレーターに接続することが可能。
▼詳細記事
コールセンターにおけるACDとは?用語定義やメリットを解説
業務の全般や一部を、外部の専門業者に委託することを指す。コールセンターにおいては、オペレーター業務を委託するケースが多い。
▼詳細記事
コールセンターのBPOとは?用語の解説とメリット・デメリット
コールセンターの運営管理システムのことで、運営にかかわるデーター集計や監視を行う。具体的には、問い合わせ件数や応対時間などのデータを集計し、状況把握や分析、予測を行う。
▼詳細記事
CMS(コールマネジメントシステム)とは?コールセンター用語を解説
顧客満足度を測定する指標のひとつで、お客様が商品やサービスを購入・利用して、どの程度満足しているかを数値化したもの。購入・利用した直後にアンケート調査を行い、フィードバックからスコアを算出する。
▼詳細記事
C SAT(顧客満足度)とは?コールセンターで重要な理由を解説
コンピュータを活用して、通話やメール、チャットなどの各種コミュニケーションツールを統合的に利用するためのシステム。CTIは、コールセンターの自動化や効率化に大きく貢献する。
▼詳細記事
コールセンターにおけるCTIとは?用語解説と導入のメリット
「Frequently Asked Questions」の略語で、特定のトピックや商品・サービスに関する「よくある質問とその回答」をコンテンツ化したもの。定型的な内容であれば、お客様がオペレーターに問い合わせをせずとも疑問や問題を解決できるため、顧客満足度の向上や業務効率化に期待できる。
▼詳細記事
コールセンターの負荷を減らすためのFAQとは?作り方のポイント
スタッフがフルタイムで勤務したときの仕事量を表す単位で、「フルタイム当量」とも呼ばれる。具体的には、FTEによってパートタイムの仕事量をフルタイム業務に換算し、何人分に相当するのかを割り出すことができる。
▼詳細記事
FTEとは?意味や計算式をコールセンターの例で解説
音声自動応答システムとも呼ばれ、お客様から入電があった際、オペレーターの代わりにシステムが一次対応の受付や問題解決までを導いてくれる機能。
▼詳細記事
コールセンターにおけるIVRとは?用語定義やメリットデメリット
商品・サービスを購入・利用したお客様の満足度や、ロイヤルティを測定するための指標。顧客体験をもとに、「今後、身近な人におすすめする可能性はどれくらいありますか?」と質問し、推奨度合いを評価してもらい測定を行う。
▼詳細記事
コールセンターの評価指標 NPS とは?分析手法や向上する方法を解説
企業や組織などに設置する構内交換機のこと。PBXは、企業内部での通話や通信を簡単に行えるように設計されている。主に、部門間などでの内線電話、外線公衆網への接続といった、電話機にかかわる管理を行う。
▼詳細記事
PBXとは?コールセンター用語解説と仕組み・メリットなどを解説
自動ダイヤルシステムの一種。事前に収集した顧客情報を元に、複数の電話番号を自動的にダイヤルさせ、接続された通話をオペレーターに切り替える。話し中や不在により、電話がつながらなかった場合は、そのコールは発信リストに戻され、次の架電が行われる。
▼詳細記事
PDSとは?コールセンター用語解説と仕組み・メリットなどを解説
1人の管理者が同時にコントロールできる部下の人数を意味する。コールセンターにおいては、SVが管理しているオペレーターの人数を示す。
▼詳細記事
SOCとは?コールセンタービジネスにおける定義をわかりやすく解説
お客様から寄せられた要望やクレーム・苦情などの声を表す言葉。得られたVOCは、商品・サービスの新規開発や改善、マーケティング戦略の策定などに活用される。
▼詳細記事
VOCとは?コールセンターで重要視すべき理由や活用ポイント
コールセンターを立ち上げる際には、今回ご紹介した運営に関わる用語を理解する必要があります。しかし、聞き慣れない言葉や実際に利活用の難しい指標が多いのも事実です。
現状、コールセンター運営に関する知識が足らず、立ち上げに不安を感じているのであれば、電話対応の全般を電話代行サービスに委託するのも有効な手段といえます。
中央事務所は専門講習を受けたプロのオペレーターが在籍しており、月間総受電数6万件(※1)、新規入電応対率98%(※2)、さらにカスタマー応対率95%(※3)を維持するなど確かな実績がございます。
「コールセンターを導入したいが、自社で行うのは難しい」とお困りであれば、企業規模に合わせ柔軟にプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
※1: 月間総受電数6万件
2021年10月1日~10月31日の期間で入電数をCTI出力により、CTIに接続しオペレーター対応をした件数を集計
※2: 新規入電応対率98%
2021年1月~2022年4月の期間でオペレーター対応数を新規入電数で割り算出
※3: カスタマー応対率95%
2022年2月~2022年4月の期間でオペレーター対応数をお客さまからのカスタマー入電数で割り算出